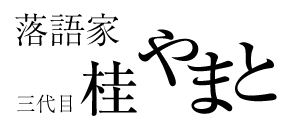この連載も最後となりました。ここまでお付き合いくださいまして、誠にありがとうございます。
千穐楽にお送りしますのは「淀五郎」の一席です。これまた歌舞伎でおなじみの「仮名手本忠臣蔵」の四段目にまつわる噺。
これは隅田川馬石兄さんに稽古をお願いしました。それが2020年11月のことで、初演したのが2024年2月の独演会ですから、かなり気長に取り組んでいたことになります。
というのも、ちょうど稽古願いした頃は特に世の中が新型コロナでピリピリムード。ソーシャルディスタンスとやらで対面でおしゃべりするのも制限があったり。
そんなこともありまして、馬石兄さんから「オレのは師匠がベースだから、これを参考にしてみて。わからないところは直してあげるから」と、雲助師匠の高座ビデオをお借りしました。だいぶお若い頃の映像でしたが、貫禄は十分でした。それをしっかり見て聴いて研究しました。真打になると前座や二ツ目と違って、「自分で考える」ことを稽古でも要求されるのが当たり前なんです。そこでこの噺でも頑張って解釈しながら稽古に臨むわけですが、なるほどこの噺はかなり難しいですねぇ。
何が難しいって、淀五郎の人物像ですわねぇ。歌舞伎役者の澤村淀五郎をどんな了見の人間に設定するかで、芸に悩む姿もガラッと変わってきます。そして、いきなり昇進できたらどんなに嬉しいだろうか……ということも、同じく階級社会に生きる落語家だから想像しやすいし、それ以上の想像も働きます。
この「それ以上の想像」というところで演者によって違いが出てくるだろうし、それが淀五郎の心理描写に反映され、お客様にも伝わっていくんだと思っています。
いや、伝えなきゃいけない。でもでも「伝えなきゃ、伝えなきゃ」と強く思えば思うほど、落語って不思議と空回りするんです。あらま、「淀五郎」の本筋に行き着いちゃった。それは聴いていただいた時のお楽しみということで。えへへ。
落語家みんなが共感できる内容の一席だと思ってお聴きいただけましたら幸いです。初演以来の口演となります。ぜひぜひ千穐楽もお運びくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。
★2025年6月21日(土)~30日(月) 鈴本演芸場主任興行「桂やまと本寸法厳選十席」詳細はこちら→ https://yamato3rd.com/?p=4729