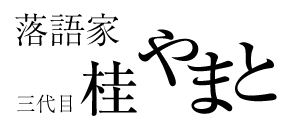6/23(月)の三日目は「三味線栗毛」をお届けいたします。私の記録を見ると、4年前のちょうど6月に初演してましたね。まだ4年しか経ってなかったっけ?? と一人で驚いているところでござんす。
目の不自由な人物が出てくる噺が落語にはいくつかあります。映画だと『座頭市』が有名ですが、落語にはそういう派手なものはございませんで。それよりも胸に迫る噺が多いように感じます。
この「三味線栗毛」は古今亭菊之丞兄さんに教わりました。演者の少ない噺ですが、菊之丞兄さんの軽妙かつ丁寧な語りが見事にこの噺にマッチしていて、私は「三味線栗毛」が好きになったんですね。
実際に稽古していただいて、さっそく覚え始めてからわかりました。この噺、難しいなと……。
いやいや、どの噺も正直言って難しいんです。よく「寿限無」や「子ほめ」とかを『前座噺』って言ってるのを聞きますけど、簡単という意味じゃありませんから。前座ほどの若手でも、とりあえずは噺のゴールまでは行けるということで。
あくまで落語は「間」「声」「表情」「人間性」等々、笑っていただけるために必要な要素がたくさんあります。特に大事なのは人生経験ですかね。その有り無しは全身から出てしまいますので。手軽に受ける落語なんて一席もありません。だからこそ一生が修行なんですよね。
さてさて「三味線栗毛」に話を戻しますが、大名の倅なのに下屋敷に住むことになった格三郎が按摩の錦木と初対面の際に、どういうわけで錦木を気に入ったのか。ここ、演者が人物像をどう捉えているか、解釈が分かれていくポイントだと思っています。私は演じ続けているうちに解釈が少しずつ変わってきて、自分なりに新たな演出を加えています。
そしてこの噺のマクラで『塞翁が馬』という故事を引き合いに出しますが、人生って本当にわかりませんよね。
落語家として精進していると、やっぱりあるんですよ。うまくいかない時なんかたくさんありますが、「あの時に聴いたやまとさんの『〇〇〇』がとても良かったからさ〜」と、ひょんなきっかけでずっと独演会に通ってくださるようなご贔屓になっていただけたり。
この日の「三味線栗毛」を聴いていただいたお客様の中から、お一人でもそんなご贔屓になっていただけたら嬉しい限りです。どうぞよろしくお願いいたします。
★2025年6月21日(土)~30日(月) 鈴本演芸場主任興行「桂やまと本寸法厳選十席」詳細はこちら→ https://yamato3rd.com/?p=4729