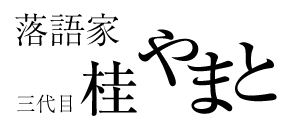さてさて、中日(なかび)となります25(水)は、「鰻の幇間(たいこ)」の一席です。幇間はそのまま「ほうかん」と本来は読みますが、この場合は「たいこ」と読ませるところが昔ながらのアバウトさ。好きだなぁ〜。
令和の世の中にも本職の幇間の方はいらっしゃいます。「太鼓持ち」という呼び方のほうが馴染みがありますよね。
実際にお座敷でお客様のお酒の相手をしたり、頼まれれば芸を披露したり。そのあたりは落語家と似ているんですが、とにかく幇間がすごいのは『お客様に逆らわない』ってえところ。落語家は平気で「いや、そりゃ違うでしょ〜!」とか言っちゃいますからねぇ(笑)。
この「鰻の幇間」は先代の古今亭志ん橋師匠から教わりました。ツルツル頭がトレードマークで、我らが志ん朝一門のまとめ役として、私も入門以来ずっとお世話になりました。感謝以外に言葉が見つかりません。
噺も12席習いましたが、志ん橋師匠の稽古は「折り目正しく」という表現がピッタリでしたね。上下(かみしも)の切り方、所作の形、声の出し方。すべて今でも大変参考になっています。話すテンポは後で変えられても、語尾が聴こえない発声なんかは指摘されて意識するようにならないと直せませんから。志ん橋師匠は特にそのことは厳しかったですね。
さて「鰻の幇間」で何を気をつけてるかってえと、ズバリ『間』ですね。うん、『間』。
落語家にアンケートでも取ってみたら面白いと思うんですが、「演じてて難しいと感じる落語は?」って聞いたら、この噺はかなり上位に入ると思います。夏の暑い盛りに客をつかまえようと彷徨う姿や、客をつかまえてからのドラマをどれだけ自然に伝えられるか……。
この噺も二ツ目からやり始めて、長いこと格闘しておりました。お蔵入りにしちゃった時期もありましたが、近年また出してみたらとてもしっくりくるようになりました。
満を持して今回のトリでお聴きいただきます。次はいつやるかわかりませんよー。どうぞお楽しみに〜!!
★2025年6月21日(土)~30日(月) 鈴本演芸場主任興行「桂やまと本寸法厳選十席」詳細はこちら→ https://yamato3rd.com/?p=4729