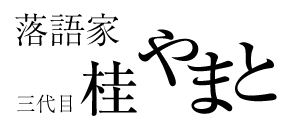6月28日。ええ、何の日だかご存じですか?
正解は「古今亭志ん生師匠の誕生日」……なんですが、当人は6月5日生まれと言ってたようなんですね。でもでも、戸籍上は間違いなく6月28日という。明治23年のことなので、こんなズレがあっても特に驚かなかったんでしょうねぇ。
ちなみに志ん生師匠は寅年で、次男の志ん朝師匠も寅年。その弟子の才賀も寅年で、そのまた弟子の私も寅年。そしてそして、私の息子が寅年の6月28日生まれなんです。かなり寅年の巡り合わせを感じませんか!!
えっ、当日は息子に誕生日プレゼントをくださるですって?? いやいや、いいですよ。どうぞお気づかいなく。
って、ただの独り言なので、さらにお気づかいなく(笑)。
そんな日にお送りしますのは「中村仲蔵」の一席です。こちらは今年1月の独演会でも演じていますが、初演したのは2017年11月の東京大神宮での『十七日寄席』でした。
11年間続いて惜しまれつつ終了したこの寄席は演芸評論家・大友浩さんのプロデュースで、私も年に2回出演させていただき大好きな会でした。
さてさて「中村仲蔵」は五街道雲助師匠から教わりました。仮名手本忠臣蔵の五段目が舞台となっています。とにかくこの噺は絶対に雲助師匠から習うんだと、実は落語家修行が始まった時には決めていました。
というのも私がまだ中大落研時代でしたが、雲助師匠がTBS『落語研究会』の放送でやっていたのを観て、めちゃくちゃ感動したからなのでした。にしても、あの時点で雲助師匠はまだ40代後半。いやはや、すごく貫禄があったのを記憶しています。
前座修行を終えて二ツ目になってからも、稽古のお願いはできませんでしたね。なんだかハードルがとても高い印象の噺だと感じていたので。
真打になってからやっと教わって、初演後は自分なりに演出を加えていますが、雲助師匠の型を大切にしながら演じています。
そしてサゲ(落ち)は今年から新たなものに変えました。これは演芸評論家の長井好弘さんも今年1月の独演会で聴いてくださった際に「あれは良いねぇ!」とお墨付きを下さいました。
演じることでお客様のハートを掴みたい。これは落語も歌舞伎も同じです。仲蔵の苦悩にも共感できるからこそ、この噺は多くの演者によって磨かれ続けるんだと思います。ぜひ桂やまとの「中村仲蔵」をお楽しみに。どうぞよろしくお願いいたします。
★2025年6月21日(土)~30日(月) 鈴本演芸場主任興行「桂やまと本寸法厳選十席」詳細はこちら→ https://yamato3rd.com/?p=4729